光陰矢の如し。
始めた時は、余裕を持って計画を立てたはずなのに、気が付いたらもう直ぐ試験本番。
勉強が進まず、試験本番までの残り時間がない、なんてことはありませんか?
せっかく受験料も払い込んであるのに、どうしましょう?
今回は、そんな試験本番まで時間がないときにどうするかについて考えます。
答えは、過去問だけが頼りです。
私の最短で仕上げた2級ボイラー
昔、ボイラー2級の試験を受ける時、役にも立たない厚い参考書を読んでいたら試験本番まで時間がなくなってしまいました。
その時は、実技講習で貰った標準問題集というのがあつたので、その問題集の正しい設問だけに丸印を付けて、その正しい設問だけを3回ぐらい読んで受験しました。
ボイラー2級の試験はは五肢択一なので、「正しいものはどれか」という問だと、正しい選択肢は一つ、「間違いはどれか」という問だと正しい選択肢は四つ有りますよね。
その正しい選択肢に印を付け、正しい選択肢だけを読んでいくのです。
基礎の無い私でしたから、間違った選択肢を読むと頭が混乱してしまします。
そんな感じで、2〜3日で仕上げました。
それで合格でした。
これはボイラー2級だからできた方法です。
もう少し難しい試験では、たぶん通用しません。
最短で仕上げる勉強法
では、一般的な試験の場合はどうするか?
これは過去問に頼るしかありません。
過去5年から10年分の過去問とその解答解説を集めて、これだけを勉強します。
では、「参考書は必要ないのですか?」
そんなことはないですよ。参考書も必要になります。
では、その方法について見ていきましょう。
まず、○○年度の□□科目の問1から始めますよね。
問題を読んで分かるところがあれば、雑用紙にチラッとメモしておきます。
基本的には、勉強していないので分からないですよね。
直ぐに、解答解説に進みます。
そこで、解説に書かれている、この問題を解くのに必要な知識を抽出します。
必要な公式、必要な法律の条文、必要な構造、等々、です。
ここで、解説に疑問があれば参考書で確認してください。
必要な知識を、まとめノートに書きだしておきます。
ここで、私は、まとめノートには付箋紙ノートを推奨しています。
詳しく知りたい方は、まとめノートの作り方 を参照してください。
次に、そのまとめノートだけを見ながら、再度問題を解いてください。
答えを見たばかりだし、まとめノートをヒントにしながらなので、解けるはずです。
ちゃんと、公式には数字を当てはめて解く、正誤問題なら理由も考えて解いてくださいね。
直ぐに確認するので、記憶に定着する可能性が増えますよ。
1問目が解けたら、次に進みます。
ここで注意点です。
難しいテクニックを使っている問題、解説に難易度が高いと書かれている問題は飛ばしましょう。
同じ難しいテクニックは出ません。
難易度の高い問題は捨てる問題です。
だから、この手の問題は、時間の無駄です。
できれば10年分(集めた過去問の全て)について、
少し考え、
まとめノートを作り、
再度解くのがベストです。
が、しかし、今は「試験本番まで時間がない」前提で考えています。
5年分の過去問が終われば、次のステップに進みましょう。
今度は本番の試験時間で、何も見ずに、最初の○○年度の□□科目の問題から解いていきます。
この段階で合格点まで達していれば、ひとまず安心とします。
また、間違えた問題は、まとめノートを見ながら解き直します。
まとめノートを見ながらでも解けない問題は、まとめノートを作り直してください。
問題を解くために必要な知識に欠如があるはずです。
時間の無駄としたテクニック問題は、もちろん飛ばしての話です。
まだ試験本番まで時間があれば、次の5年分に取り掛かってください。
ただし、試験本番2~3日前には、まとめノートに専念する時間です。
試験本場時までに、まとめノートの知識を完全なものにしてください。
あやふやな知識は、試験で役に立ちません。
まとめ
この方法で、本当に試験に合格するのか?
答えは、運が良ければ、合格します。
こんな付け焼き刃的方法で合格するなら、みんなやってますよね。
ただし、多くの試験で、点数はアップするはずです。
中には、一度出た問題と同じ問題は出ない試験もあります。
例えば、電験1種、2種の2次試験での論説問題がそれです。
この手の試験には付け焼き刃的方法は、通用しません。
しかし、論説問題がダメでも、計算問題には通用するので、計算問題で取れる問題は増えます。
あくまで、試験本番まで時間がない時の、付け焼き刃的方法であることは理解しておいてください。
またこれは、試験本番から逆算する を短時間用に応用したものです。
興味のある方は、一読してみてください。
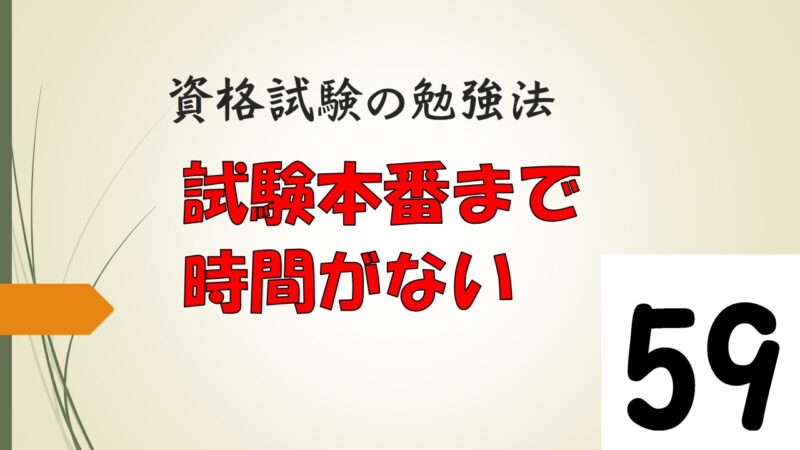


コメント